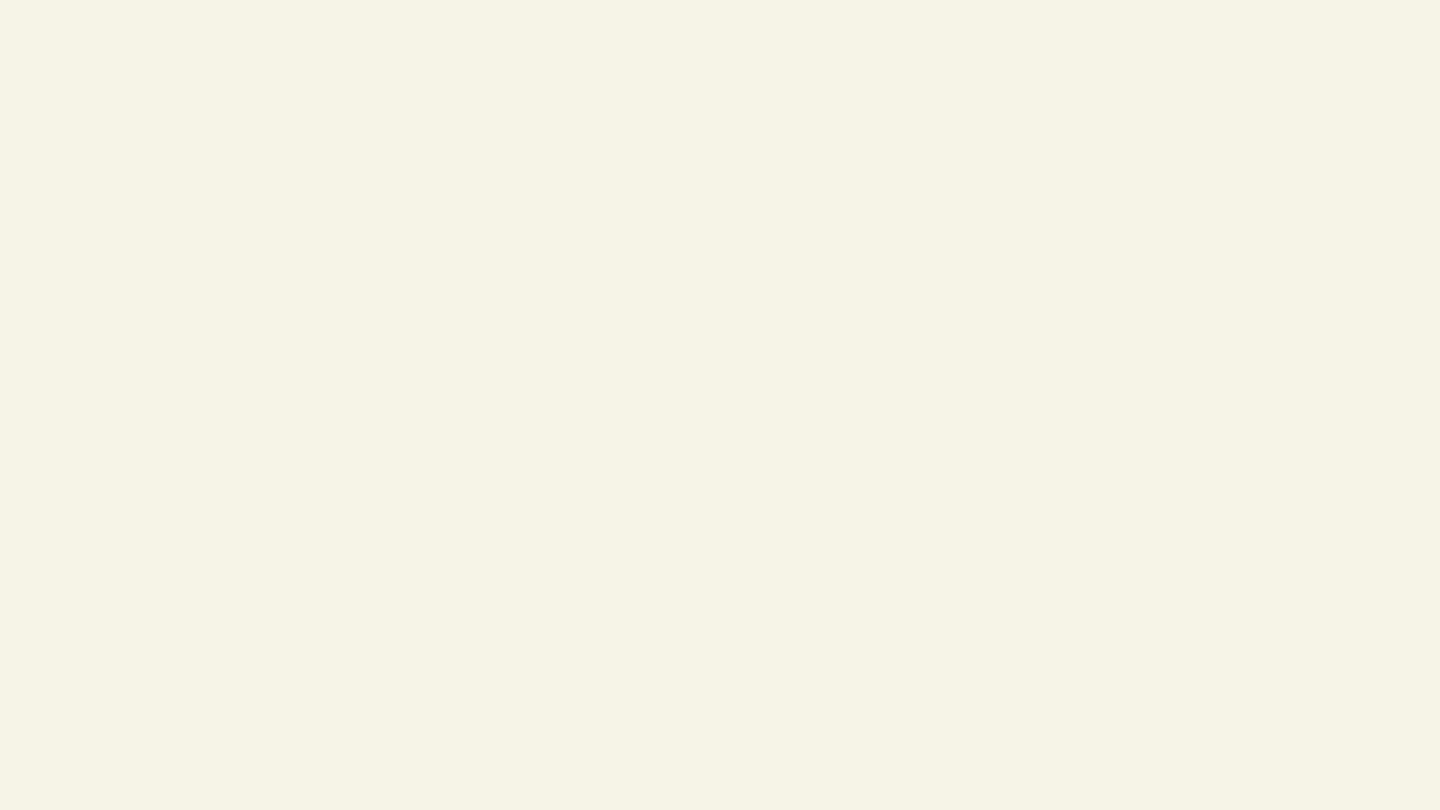当社では、生活保護を受けておられる方の転居のご相談もお受けしています。自治体と連携し、スムーズに転居が出来るようにサポートしますので、安心して、ご相談ください。
ここでは、生活保護を受けている方の転居手続きについて、ご説明します。
生活保護を受給している方の転居手続き
①ケースワーカーに相談し、転居費用が支給されるか確認しましょう
生活保護を受けておられる方は、自治体が定める条件を満たせば、転居費用が支給されます。「もっと広い部屋に住みたい」、「買い物に便利な場所に引っ越したい」などの理由では条件を満たさず、転居は自己負担になります。
例えば、「老朽化による取り壊しで退去を求められた」、「賃貸住宅のオーナーから強く値上げを要請され、住宅扶助の上限金額を超えてしまう」、「高齢や病気の影響で今の住宅では安全や健康が確保できない」などの理由では転居が認められる場合があります。
先ずは、自治体のケースワーカーに相談し、転居の確認を取りましょう。
②転居先を探しましょう
次に転居先の賃貸住宅を探します。その際には、不動産会社に生活保護を受けていることを伝え、家賃が住宅扶助の範囲内の住宅を探して貰いましょう。
注意が必要なのは、管理費や共益費です。管理費や共益費は、住宅扶助から支給されず、生活費である生活扶助の中から入居者が払う必要があります。出来るだけ、管理費や共益費の安い物件を探しましょう。
③初期費用を確認し、物件の許可を貰いましょう
希望物件が見つかれば、不動産会社から初期費用の明細を貰います。初期費用とは、敷金、礼金、火災保険料、家賃保証料、鍵交換費用、仲介手数料、前払い家賃などです。自治体により初期費用の上限金額や支出項目が決まっているので、ケースワーカーに初期費用の明細を提出し、確認しましょう。
また、転居先の物件にエアコンや照明器具、コンロ等の生活するための必需品が付いていない場合は、家電什器費が支給されます。これもケースワーカーに確認が必要です。
ケースワーカーに物件の許可を貰えば、不動産会社に入居申込を行い、審査を受けます。
④賃貸借契約を結びます
入居審査に通れば、具体的に入居日を決め、賃貸借契約を結びます。事前に賃貸借契約書のコピーを不動産会社から取り寄せ、ケースワーカーに確認して貰いましょう。契約にあたっては、初期費用の支払いが必要です。ケースワーカーに初期費用が支給される日を事前確認し、契約日を決めます。
契約の当日は、必要書類と印鑑を持参し、契約を行います。ケースワーカーに初期費用の領収書の提出が必要ですので、必ず、領収書を貰いましょう。
⑤引越し業者を選定し、引越しする
入居日を決めたら、引越し業者を選定します。引越し業者は、原則、3社から見積もりを取り、最も安い業者を選ぶことになります。見積書をケースワーカーに提出し、引越し業者を決定、引越しを行います。
当社の転居サポートについて
このように、生活保護を受けておられる方が転居される際には、一つ一つ、ケースワーカーに確認しながら進める必要があります。当社では、ケースワーカーと直接やり取りしながら、転居のサポートが可能です。
いま、生活保護を受けておられる方で転居を希望される方は、安心して、当社にご相談ください。